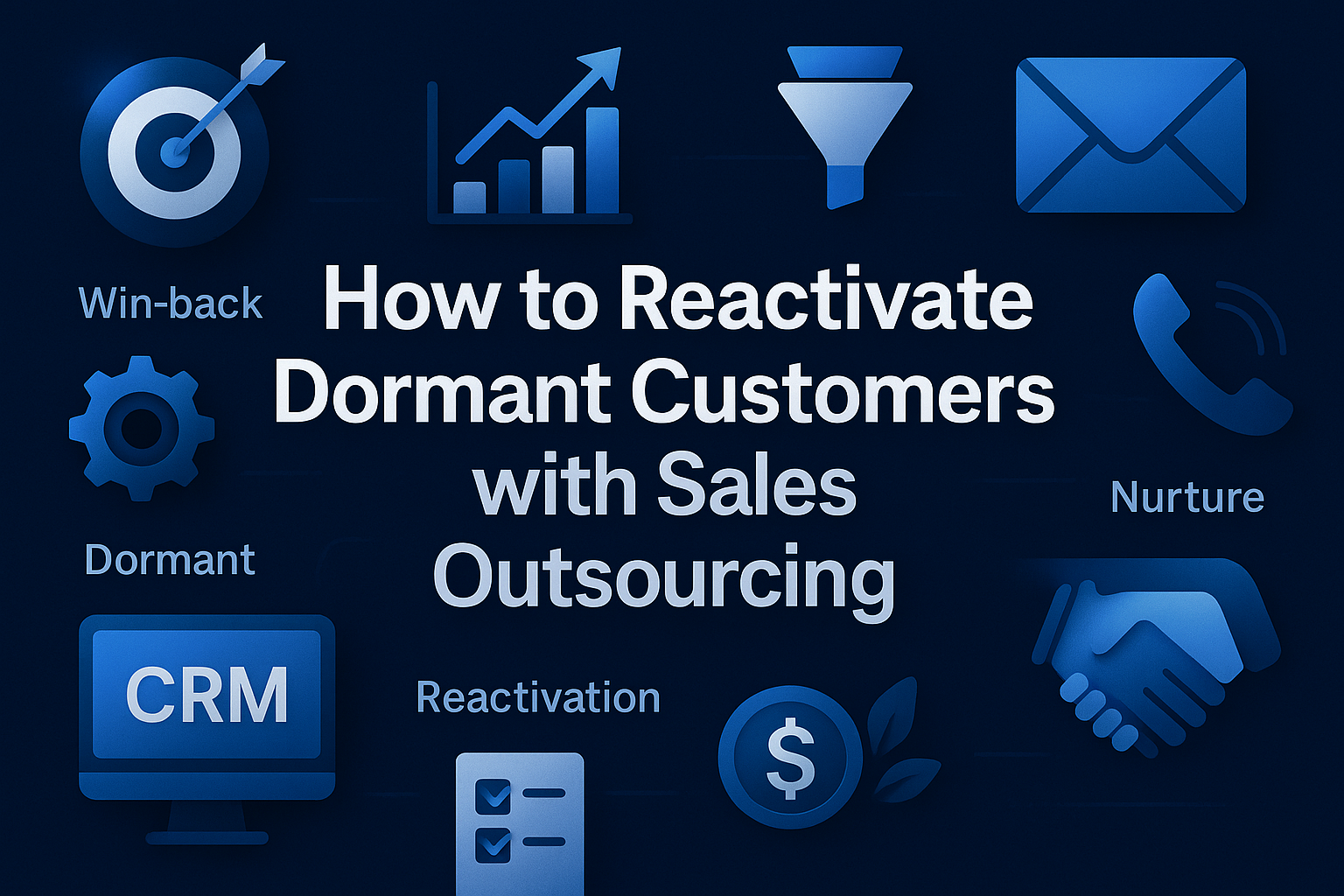
– 「任せたら全部やってくれる」は本当か? – クライアント側の協力が必要な理由
営業代行は、新規顧客の獲得や営業リソースの補完手段として、さまざまな業界で導入が進んでいます。しかし一方で、「営業を外部に任せたのに思ったほど成果が出なかった」という声があるのも事実です。
その原因の多くは、**営業代行に対する“誤解”や“過度な期待”**にあります。
本記事では、営業代行を導入する企業がつまずきやすい「よくある勘違い」と、営業代行の正しい位置づけと活用方法について解説します。
目次
1. よくある勘違い①:「営業を丸投げすれば売上が上がる」
最も多い誤解は、「営業代行に依頼すれば、すべてを任せて売上まで勝手に伸ばしてくれる」という期待です。
実際には、営業代行は**自社の商品やサービスを理解し、それを市場に伝える“パートナー”**であり、単独で成果を保証する存在ではありません。
とくにBtoB商材の場合は、
- ターゲット設定
- 提案資料の準備
- 顧客対応のフロー整備
といったクライアント側の情報提供や体制構築が不可欠です。
営業代行は“魔法の杖”ではなく、「設計・連携・改善」を前提とした共同プロジェクトと考えるべきです。
2. よくある勘違い②:「自社に営業体制がなくても成果が出る」
営業リソースが足りないスタートアップや小規模事業者にとって、営業代行は非常に心強い存在です。しかし、「社内に営業担当が一切いない」「リードに対応できる人がいない」状態では、せっかく獲得した見込み顧客が取りこぼされることもあります。
営業代行が担うのは多くの場合、初回接点の創出や商談のセッティングまで。その後の商談対応やクロージングは、クライアント側の担当者が対応する体制を整えておく必要があります。
また、営業活動の改善には、代行会社との定期的な情報交換も不可欠です。「放置型運用」では、どんなに優れた代行会社でも成果を出すのは難しくなります。
3. よくある勘違い③:「成果報酬だからリスクゼロ」
営業代行の中には「成果報酬型(アポ獲得や受注に応じた報酬)」を採用しているサービスもあります。確かに、成果に対してのみ費用が発生するため、コストの透明性は高まります。
しかし、「完全にノーリスク」という考え方には注意が必要です。
- 成果に至らない場合でも、商談準備や文面作成には時間と工数がかかっている
- 営業代行側が成果を追いすぎるあまり、質より量のアプローチになりがち
- 成果が出なかった原因が、商品力・価格設計・ターゲティングの問題であることもある
つまり、「成果が出なかった=代行会社の失敗」とは限らず、営業プロセス全体のどこに課題があるのかを共に分析し、改善していく姿勢が求められます。
4. 成果を出す企業が実践している「協働のスタンス」
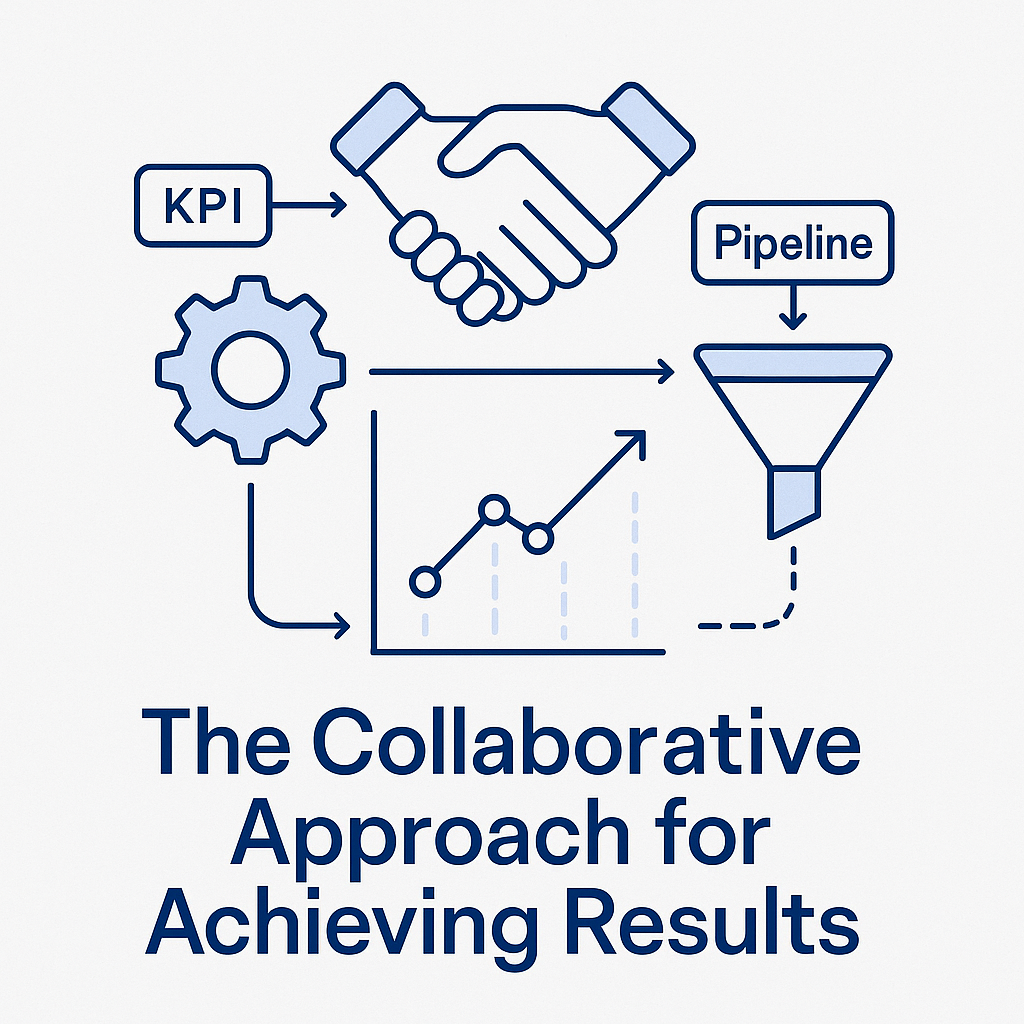
営業代行をうまく活用している企業には、いくつかの共通点があります。それは、「外注」ではなく**“共に営業を創るパートナー”として営業代行と向き合っている**という点です。
具体的には、以下のような取り組みが成果につながっています。
- 初期にしっかりとしたサービス説明資料やトークスクリプトを提供している
- 定例ミーティングを設けて、現場の温度感や改善点を共有している
- 商談後のクロージングプロセスまでを含めた全体設計を行っている
このような「協力体制」があることで、営業代行はクライアントの事業や商品を深く理解し、より高い再現性をもって営業活動を展開できるようになります。
まとめ:営業代行を“任せきり”にしない。共に成果をつくる意識がカギ
営業代行は非常に強力な営業リソースですが、その効果を最大化するには、「依頼する側にも責任がある」という意識が必要不可欠です。
- 丸投げは失敗の元
- 社内対応の受け皿を整備
- 定期的な情報共有で改善サイクルを構築
この3点を意識することで、営業代行は「外注業者」から「成果を共に追うパートナー」へと変わります。導入を検討している企業こそ、営業代行の“正しい使い方”を理解することが、成果への第一歩です。